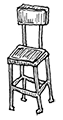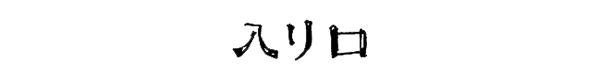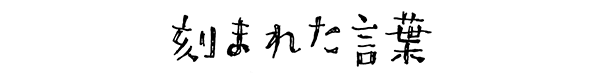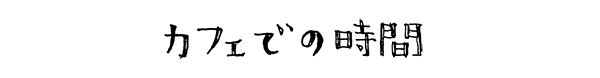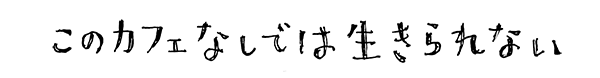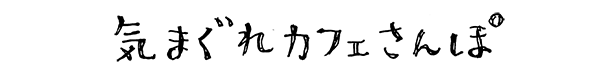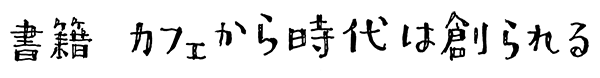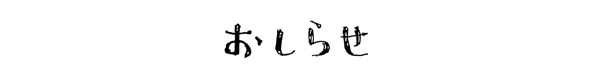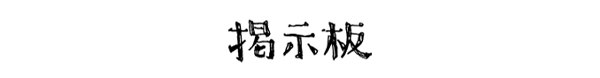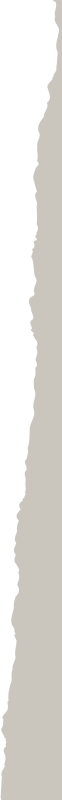
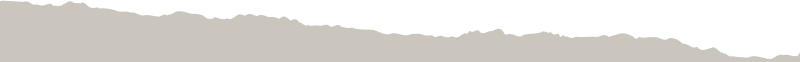
カフェー
勝本清一郎
文学や美術とカフェーとの交渉の日本におけるいちばん古いところは、明治二十一年四月、東京下谷区上野西黒門町二番地、元御成道警察署南隣に可否茶館[かひいさかん]が初めてできたとき、硯友社のまだ若かった作家たちが出入りした話からである。この可否茶館が日本におけるカフェーの最初であるからこれより古いという交渉はない。江戸時代の水茶屋まで範囲に入れるとすれば司馬江漢の銅版画「両国橋」に両国河岸のよしず張りの水茶屋の情景、春信のにしき絵に笠森稲荷茶店の図、政信の墨刷りにしがらき茶店の図その他があり、春信の作品は後の邦枝完二の小説「おせん」や小村雲岱の版画の素材になっている。
しかし水茶屋の系統は別としよう。これに似たものはいまでもエジプトやトルコへゆくと、やはり道ばたの茶店のような構えで、柄のついたパイプ型真鍮製の小容器でコーヒーを濃く煮ている光景にぶつかるが、そういうコーヒーの飲みかたは日本に伝わらなかった。日本のコーヒー、コーヒー店も西欧系である。
硯友社の機関誌「我楽多文庫」の公刊第一号(明治二十一年五月)に「下谷西黒門町可否茶館告条」という石橋思案の一文が出ており、それに開業したばかりの可否茶館をさして「西洋御待合所」とうたってある。
この「我楽多文庫」が「文庫」と改題されてからの第十九号(明治二十二年四月)には川上眉山の「黄菊白菊」という小説の第五回が出ていて、そこに可否茶館の場をとらえた文章とその場を描いたさし絵がある。画中の文字は紅葉の筆跡である。
この文章と絵が日本の文芸・美術に日本のカフェーが登場した最初である。絵を見ると驚くことに和服の女学生が非常に長いはおりを着て、洋ぐつをはいている。男の長いはおりは江戸時代の天明年間に流行して、清長の絵に残っているが、外とうのように長い女のはおりというものは、茶ばおり流行のいまの日本人の記憶にはもうない。文章はこんな文体である。
「敬三は下谷の可否茶館に。そゞろあるきの足休めして。安楽椅子に腰の疲を慰め。一碗の珈琲に。お客様の役目をすまして。新聞雑誌気に向いた所ばかり読ちらして余念と苦労は露ほどもなかりし。隣のテーブルには束髪の娘二人」
石橋思案の「告条」には「茶ばかり飲むも至つて御愛嬌の薄き物と存じトランプ、クリケット、碁将棋、其外内外の新誌は手の届き候丈け相集め申置候」とか「文房室には筆硯小説等備へつけ、また化粧室と申す小意気な別室をもしつらへ置候へば其処にて沢山御めかし被下度候」とかある。クリケットという遊びは私の小学生時代、慶応義塾幼稚舎ではまだ行なわれていた。
可否茶館の開業にさいしては「可否茶館広告、附、世界茶館事情」というパンフレットが配布された。それによると、パリのカフェーの元祖はサンゼルマン街にアルメニア人パスカルの開業したもので、一七八五年版ジュラウルの「巴里名所記」にそのことが出ているよしである。
なお茶館という名称からもわかるとおり、中国茶館の系統も引いている。主人は長崎生まれの鄭永慶[ていえいけい]という人で、石橋思案も長崎生まれだったことから硯友社の面々が後援した。思案はこの可否茶館を会場にして東京金蘭会と称する男女交際会の会合をしばしば催した。その会では当時の帝大生たちが流行の清楽合奏などしたが、主宰者の思案もまだ二十歳代の学生だった。
可否茶館は二階建ての洋館で庭も二百坪ほどあった。二階の席料が一人一銭五厘、階下は広間で無料。コーヒーのねだんは牛乳を入れないのが一杯一銭五厘、入れたのが二銭、菓子付きで三銭。酒類はベルモット二銭五厘、ブランディー三銭、ぶどう酒二銭七厘、ビールがストックビール小びん十五銭。たばこは鹿印二十本二銭……。いまではこれらのねだんはすべて五千倍を越えている。
ただし可否茶館は客がきわめて少なく、いついってもすいていたよしで、まもなく廃業した。したがって初期カフェー文学は、文明開化思潮の中でハイカラ風俗小説を目ざしていた初期硯友社の作家たちによってもそれきり発展せずに終わった。
[後略]
「日本の名随筆 別巻3 珈琲」作品社
1991(平成3)年5月25日第1刷発行