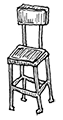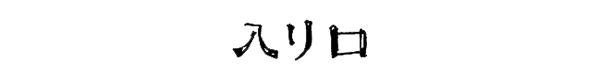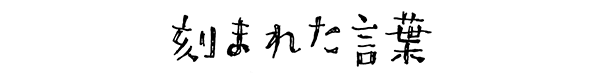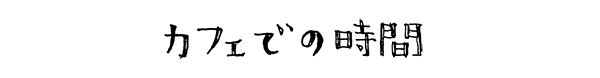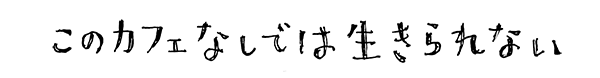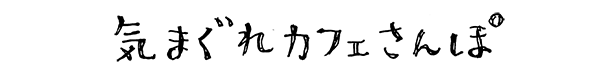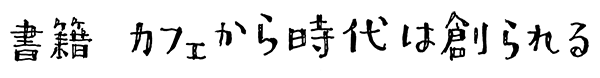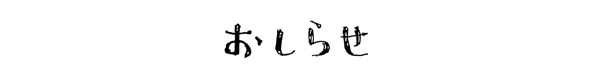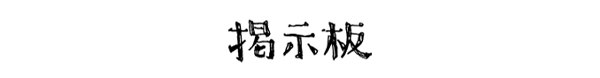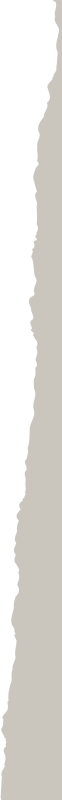
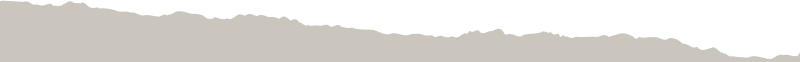
喫茶店の時間
影山知明
北の、海沿いのまちにあるその喫茶店は、名前を「光」といった。
アーケード街に連なるその店は外観が古びたレンガづくりで、重厚感ある扉を開けて入る店内もうす暗く、店名はむしろ「闇」が似つかわしいとさえ思ったが、もうかれこれ八〇年続いているというのだから文句のつけようもない。席に座ると昼間だというのにそこは本当に暗く、本を開いても文字を読むのがつらいくらいに暗い。ツライクライニクライ。
珈琲をオーダーすると、スプーンに角砂糖が二つ乗って出てきた。ああ、森進一の歌は本当だった。ここは襟裳岬からは二五七・四キロも離れているというのに。歩いていったら、ゆうに五十三時間はかかるというのに。それか、海沿いの人々の風習はどこでもそうだと言うのか。確かに言われてみればこの店だって、悲しみを暖炉で燃やし始めていておかしくない風情だ。ぼくはその角砂糖がひと粒三グラムであることを知っていた。およそ十二キロカロリーだということを知っていた。さっきまで、その何倍何十倍ものカロリーのスナック菓子を食べていたというのに、なんとなく気が咎めて、角砂糖はスルーすることにする。人間は非論理的な生き物だ。うす暗さのなかでも、珈琲の色が漆黒であることがわかる。
となりを見ると、なんということだ。カステラまでついてきた。というか見た目はパンだ。一つ一つが包装されていて、窒素充填がなされているのかパンパンにふくらんでいる。パンパンのパン。食べるとパサッとしていてふうわり甘い。まさかこんなところで角砂糖二つ分を即刻取り返すことになるとは。さっきの決断から一分と経っていないのに。
暗闇に目がなれてまわりを見渡すと不思議な調度品に囲まれていることがわかった。船の舵、細かな細工の施された舵、使いこまれて黒光りする舵、帆船の模型、青い目のドレスを着た人形、ランプ、ランプ、ランプ。ここが港まちであることを思い出す。いくつもの柱時計。壊れているのか、それぞれが別の時刻を指している。中には動いているものもあるが、それらは時間も分も、どこか別の場所の時を刻んでいる。BGMはショパン。
本を読むことはあきらめた。持ってきたのが「ブランド優位の戦略」だったのもよくなかった。これが古典文学か何かだったら違う気持ちになっていたのかもしれないが……。いや、きっとそうでもない。本を開かなくたって、ここにはもう十分すぎるくらいに物語のかけらがある。
この店は、海の男たちにとっての光だったのだろうかと思う。
長い航海、三六〇度ぐるりと海に取り囲まれる日々を経て、はるか舳先向こうに陸地が見えてきたとき、男たちの胸に去来するのはどんな思いだったろう。網にはたくさんの獲物。日焼けした肉体。深い夜。最初頼りなく、しかし徐々に力強く、まちの光が見えてくる。
「─まあでも、最初はビールかな」
思い直す。
この暗闇を求めて集まってくるのは、いったいどんな人間たちだろう。
もう一年前になるだろうか。雨のなか、傘を忘れ、濡れながら歩いたときのことを思い出した。そのときぼくは悲しかった。傘を忘れ、雨に濡れたから悲しかったのではなく、悲しかったところに雨が降ってきて、濡れたのだ。なんで悲しかったのかは覚えていないが、とにかく悲しかったことは覚えている。ああ、その前に立浪と口喧嘩をしたんだ。雨はそれなりの雨脚だったから、頭が濡れ、ジャケットが濡れ、カバンが濡れた。「ああ、雨が降ってきちゃったな」。そう思っていた。
でも、不思議と傘は欲しくなかった。
予報外れの雨で、その日はスーツに革靴だったからそれへのダメージは気になった。妻になじられるかもしれないなとも思った。だってこの間、革靴でサッカーをやったときにはなじられたから。そこにボールがあって、娘がいて、蹴ってきたなら、そりゃあ蹴るだろうに。客観的に見れば、状況はどんどんマイナス方向に向かっていた。これで雨がカバンに染み込んで、パソコンがお陀仏にでもなったら目も当てられない。でもそのとき、ぼくの主観から見る世界は悪くなかった。なんというか、そのときの自分にはずぶ濡れになっていく自分がお似合いで、世界が自分を置いてけぼりにしていない感じがして、気分がよかった。
喫茶店の暗闇も、そういうことなのかもしれないと思った。
喫茶店の暗闇は誰の悲しみも解決はしないのだろうけど、一緒になって悲しみの時間は刻んでくれるかもしれない。「そうだな、まあそういうこともあるよな」って。酒が入って、軽く酩酊して、嫌なことも忘れられるというのとも違う。寄り添ってくれる感じ。暗闇が、食器のカチャカチャいう音や、湯気や、挽かれた珈琲豆から立つ香りを引き連れ、流れていく。「ふうう」。深い嘆息のうちに、ハッと、自分にも自分だけの時間が流れていることを体が思い出す。「そうだよな」。いつの間にか自分が、他人の時間を生きてきてしまっていることに気づいて切なくなる。
カップに半分残った珈琲をぐるぐる回すと、黒い波間にランプの光が揺れた。BGMは「雨だれ」に変わっている。よくできてる。ショパンも、雨とか夜とか、きっと好きだったんだろうなと思う。だったら、この喫茶店も気に入るかもしれない。ショパンがさっきのカステラを食べたら、ショパンがパンパンのパンだ。
光に虫が集まるように、悲しみを抱えた人間たちは、見えない力に引かれ暗闇に集まるのかもしれない。
テーブルの上には、昔ながらの小さな占い機があった。一〇〇円入れてガチャンコするやつ。正式名称、なんていうんだろう。まだ作っている人いるのかな。いつからか上の部分がルーレットになっていた。昔は灰皿だったような気がするけど。「おとめ座」のところにコインを入れ、ガチャンコしてみる。巻物状になった占いが出てきた。広げてみると……、凶。ここでも世界は、ぼくを置いてけぼりにはしなかった。
外に出て時計を見、目を疑った。二五分しか経っていなかった。背中越しのレンガ造りが、心強い。
やっぱりこの店には、光という名がよく似合うと思った。
夕暮れのまちに、潮の香りがした。
※その後、検証いたしましたところ、「襟裳岬」では珈琲が二杯目なのであって、角砂糖は一つであることが確認されました。ここにお詫びして訂正させていただきます。
※本稿は、事実を基にしたフィクションです。
──喫茶の文体『喫茶店の時間』より